JAASでは、「JAASフェロー等の称号制度規程」(2024年7月5日理事会承認)に基づき、このたび4名の方に名誉フェローの称号を授与いたしました。今回、名誉フェローとなられたのは、磯谷桂介氏、梶田隆章氏、豊田長康氏、永野博氏(五十音順)です。2025年5月末から6月初めにかけて、代表理事をはじめとする理事と名誉フェローの方々との顔合わせ会が開催され、活発な意見交換が行われました。本会合の目的は、JAASのこれまでの活動や組織体制の変遷、2024年度の主な事業実績、そして今後の計画について名誉フェローの皆様に包括的にご説明し、それに対するご意見を伺うことにありました。名誉フェローの皆様には、日本版AAAS設立準備委員会の時代から、JAASの発展を温かく見守り、ご支援いただいています。当日の会では、それぞれの専門的な視点から、「日本の科学を、もっと元気に!」するための貴重なご意見を多数いただきました。こうしたやりとりの内容は、今後のJAASの活動や運営に順次反映してまいります。
顔合わせ会の日程と参加者は以下の通りです。
| 日時 | 2025年5月30日(金) 11:30~12:30 | 2025年5月30日(金) 19:00~20:00 | 2025年6月2日(月) 11:45~12:45 | 2025年6月4日(水) 11:30~12:30 |
| 参加者 (敬称略) | 永野博 北原秀治 深澤知憲 吉田智美 | 豊田長康 北原秀治 深澤知憲 吉田智美 | 磯谷桂介 北原秀治 深澤知憲 吉田智美 | 梶田隆章 北原秀治 深澤知憲 吉田智美 黒ラブ教授 宮原聖子 |
永野 博 氏
<JAASの未来と日本の科学が抱える構造的課題>
永野氏は、JAASが日本の科学振興において、より戦略的かつ影響力のある存在となるための提言をされました。10年後を見据えた明確なビジョンを持つことにより、活動の一貫性と持続可能性が高まることを強調されました。また、JAASの存在感を高め、エビデンスに基づくデータの蓄積につなげるために、旭硝子財団の「環境危機時計」のように、特定のテーマ(例:若手研究者の待遇)に関する毎年のアンケート調査を通じた定点観測の実施を提案いただきました。NPOであるJAASの運営および財政については、永続的な活動を実現するために、ボランティアベースからの脱却と、適切な経営体制の構築が不可欠であるとのご意見をいただきました。企業や財団からの支援とのバランスの図り方、会員数の増加による影響力向上についても議論が交わされました。さらに、永野氏は日本の科学が抱える構造的課題として、以下の3点を挙げ、いずれも研究者が狭い世界に閉じこもらず、多様な価値観に触れることの重要性を訴えられました。
- 文理分断の教育: 日本特有の中高段階からの文理選択の見直しや、大学入試改革も含めた提言の必要性。
- インブリーディングの是正: 若手研究者が同じ大学にとどまることで視野が狭くなる現状を打破するため、大学・研究機関間の人事交流・移動の促進。
- 海外経験の不足: 海外へ出る研究者の減少に対し、大き目な科研費の応募要件に1年以上の海外滞在経験を義務づけるなど、制度的に海外留学・滞在を促進し、多様な人材を育成する必要性。
さらに、海外の日本人研究者ネットワークとの連携の可能性など、多角的な視点から課題が提示されました。また、研究者を取り巻く環境の改善にあたっては、メディアとの連携が不可欠であるとの認識も共有されました。メディアの商業主義やジャーナリストの専門知識不足といった課題を認識しつつも、より直接的な対話を通じて、ジャーナリストとともに科学を盛り上げていく必要性が強調されました。加えて、ドイツの国立科学アカデミーに関する話題が挙がり、これによってJAAS公式WEBサイトに掲載されているJAASの位置づけ表におけるドイツの記載部分について、追記・修正が行われました。

豊田 長康 氏
<JAASの役割と日本の研究力向上への提言>
豊田氏は、JAASの活動が研究者だけでなく、学生、企業、一般市民を巻き込む点において、従来の日本学術会議とは異なる優れた方向性を有しており、その拡大に期待していると述べられました。一方で、JAAS単体で研究環境の改善に取り組むには限界があるため、政府関連組織との連携を強化し、JAASのイベント等を通じて相互理解を深めていくことが重要であると提案されました。また、豊田氏は、日本の研究力低下を憂慮するシニア層の研究者コミュニティとの連携も視野に入れる必要性を強調されました。これは、現在の研究費が若手に偏重している現状に対し、45歳以上のシニア研究者への支援の重要性を指摘したものです。ノーベル賞受賞者の多くが中高年である事実も踏まえ、年齢による資金配分が必ずしも適切でないという声が上がっており、この認識は参加理事とも共有されました。研究力の低下の主因は、研究者数や研究時間の減少といった「人的環境の劣化」にあるとされ、競争的資金の増加だけでは解決できないという見解が示されました。
さらに、豊田氏は、政府による「選択と集中」やパフォーマンス評価に基づく政策について、効果が薄く、むしろ逆効果を招いていると批判されました。特に日本の研究力低下の主因として、以下の4つの政策的要因を挙げられました。
- 2000年頃の国家公務員削減および大学院重点化政策
- 2004年の国立大学法人化
- 新医師臨床研修制度の導入
- 2006年の薬学部6年制導入
これらの施策は、地方大学や医学・薬学系の研究力に大きな影響を与え、研究時間と研究人材の減少という深刻な問題を引き起こしたとされます。特に薬学・医学分野においては、教育負担の増加により研究時間が圧迫されており、薬学教育の臨床重視への転換も研究力低下に影響しているとの考察が示されました。また、医師の働き方改革によって、医学研究へのさらなる悪影響が懸念されていることにも触れられました。医師が過重労働を強いられ、研究・教育・臨床の三立が困難になっている現状が問題視されました。海外の事例も参照されながら、政策的視点からの具体的な対策の必要性が示唆されました。特に国立大学では財政難や人員削減が深刻であり、特に基礎医学分野では教員ポストの減少が顕著です。研究力の維持・強化には、明確な目標に基づいた資源配分と環境整備が不可欠であると述べられました。

磯谷 桂介 氏
<JAASの強みを活かした科学振興とブランド戦略>
磯谷氏は、JAASの活動について非常に明確かつ有意義な説明があったと評価し、とくに「JAASの特色」と「今後の事業の方向性」について意見を述べられました。JAASは「日本を科学で元気にする」という理念のもと、分野や所属を超えて科学技術の振興・普及に取り組んでおり、科学好きのユニークな人材が緩やかにつながる「分散型の自立組織」としての強みを持っています。また、研究環境の改善、社会との連携、コミュニティ活動を担う三つのワーキンググループの運営が組織の基盤を支えている点も高く評価されました。今後の方向性としては、JAASのブランド戦略の確立が重要であり、分野横断的な科学振興組織として国内外で信頼される存在になるためには、グローバルな視点を持った広報活動が必要であると指摘されました。具体的な提案としては、「学生アイデアファクトリー」のような若手育成事業の継続・拡大が挙げられました。これは、JAASの応援者を増やし、ネットワークの拡充にも寄与する施策とされています。さらに、他組織との連携強化も重要であり、サイエンスアゴラとの共催をはじめ、他のイベントへの積極的な関与によってJAASの認知度を高める戦略が提案されました。また、科学に関心を持つインフルエンサーとの連携、学校教育機関との協働、企業や自治体、NPOなど多様な主体とのパートナーシップの推進も示されました。これらにより、JAASの活動が社会全体に広く根ざすことを期待されました。
磯谷氏は、最終的にはJAASが研究環境の改善、人材育成、科学のモニタリング・評価などにおいて信頼され、市民からも支持される「科学振興といえばJAAS」というブランドの確立を期待すると述べられました。内部体制の強化と外部への発信とのバランスの重要性については、参加した理事とも認識が共有されました。また、会員数増加の課題についても議論がなされ、科学振興活動の事例集の作成、優れた取り組みに対する表彰制度の導入、アンバサダー制度の活用、インフルエンサーの起用といった具体的なアイデアが挙がりました。
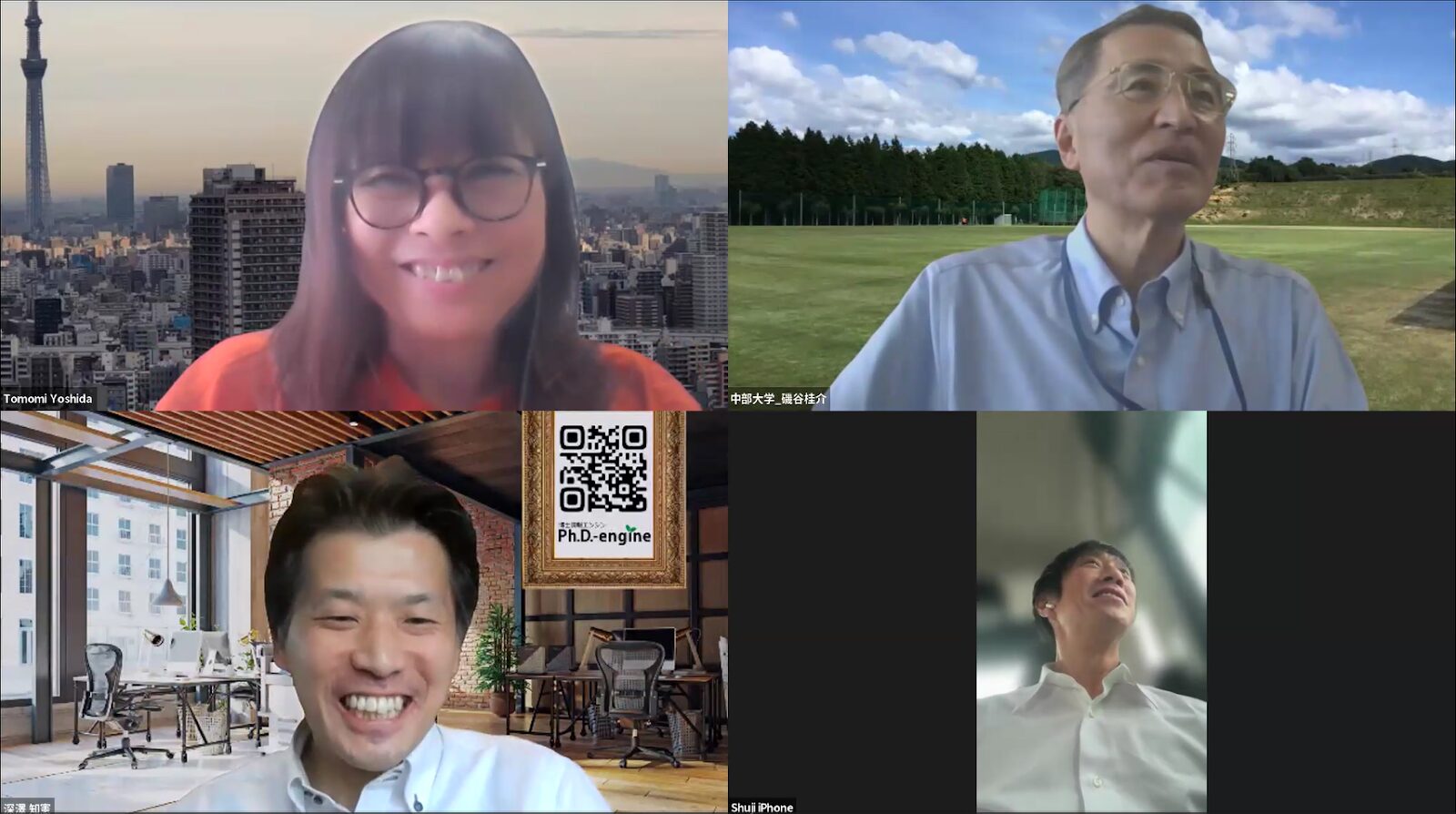
梶田 隆章 氏
<JAASの持続可能性と日本の科学振興への提言>
梶田氏と参加した理事との間では、組織の持続可能性、会員獲得の戦略、基礎研究の価値、日本の国際的プレゼンスなど、多角的な議論が交わされました。梶田氏はJAASの活動を高く評価される一方で、会員数が約220名と少ない現状を指摘し、今後は活動に共感する仲間を増やし、長期的に機能する持続可能な仕組みを構築する必要性を強調されました。特に、学生など若い層に向けた無料会員制度の検討など、会員拡大に向けた取り組みの必要性が示されました。これに対して理事からは、国内では学協会や企業との連携、国外では在外日本人研究者コミュニティやメディアとの協力体制について紹介があり、それに対する梶田氏のご意見をいただきました。梶田氏は、現状では組織が熱意に依存しすぎている側面を懸念し、制度的な支えを持った運営体制の重要性を指摘されました。また、理事からは「科学に対する無関心層へのアプローチの難しさ」や「活動の偏り」に関する課題について意見を求められました。梶田氏は、協力に前向きな姿勢を示されつつも、まずは科学に関心のある層や科学関係者を対象とする方が大切ではないかと助言されました。その上で、JAASの認知度向上や賛同者の集め方の見直しを図り、より幅広い層への浸透を目指す必要があるという認識が共有されました。さらに梶田氏は、日本における基礎研究の国際的なプレゼンス低下にも言及されました。基礎研究は未来の社会を支える「種」であり、応用研究や即時的成果への偏重に対して警鐘を鳴らされました。科学技術予算の配分や大学の研究環境の変化が、基礎研究の持続性に影響を及ぼしている点も強調されました。最後に、JAASが引き続き日本の科学振興に貢献し、社会に科学の価値を広く伝えていくことの重要性が確認され、今後もJAASへのご支援をいただく旨のお言葉を頂戴しました。

文責:北原秀治、吉田智美
